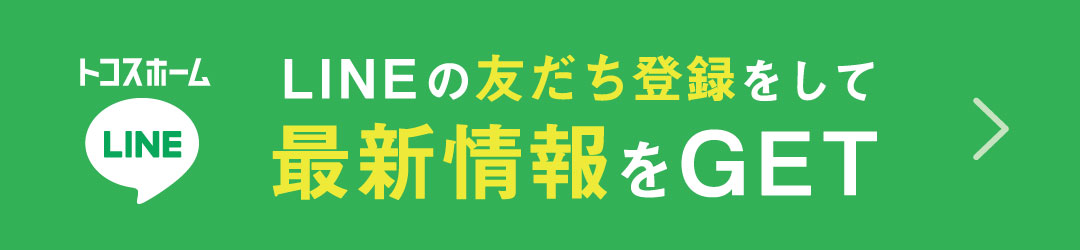長期優良住宅のメリットは?デメリットや申請費用・補助金、税制優遇まで解説
目次
鳥取・島根の注文住宅なら長期優良住宅が標準仕様のトコスホームへ
マイホームを建てる際、「長期優良住宅」という選択肢を耳にしたことはありませんか?「税金が安くなる」「補助金がもらえる」といった話を聞いて興味を持ちつつも、具体的にどのようなメリットがあるのか、自分にとって本当に必要なのか判断に迷っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、長期優良住宅の認定基準から、2025年最新の税制優遇や補助金制度、さらにはデメリットまで詳しく解説します。
そもそも長期優良住宅とは?

長期優良住宅は、単に「長持ちする家」というだけではありません。国が定めた厳格な基準をクリアし、将来にわたって安心・快適に住み続けられることを公的に認められた住宅です。以下では、その制度の背景から認定基準まで、長期優良住宅の全体像を詳しく見ていきましょう。
国が定める「長く住み続けられる家」の基準
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を指します。この法律は2009年に施行され、住宅の質を向上させることで、私たちの暮らしをより豊かなものにすることを目指しています。
制度創設の背景には、日本特有の住宅事情があります。日本の住宅の平均寿命は約30年といわれており、イギリスの77年、アメリカの55年と比較すると極めて短いのが現状です。国は従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものをつくって、きちんと手入れをし、長く大切に使う」ストック型の社会へ転換することで、環境負荷の軽減と住宅にかかる生涯コストの削減を目指しているのです。
この取り組みは着実に成果を上げています。2021年度末時点で、新築される一戸建て住宅の約4戸に1戸が長期優良住宅の認定を受けており、累計認定戸数は159万戸を超えました。多くの人が、質の高い住まいの価値を認識し始めている証といえるでしょう。
認定を受けるためにクリアすべき性能項目
長期優良住宅として認定されるためには、国が定めた厳しい基準をクリアする必要があります。「なんとなく丈夫そうな家」では認定は受けられません。具体的には、以下の8つの性能項目すべてにおいて基準を満たす必要があります。
| 性能項目 | 認定基準の概要(戸建住宅) |
| 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(劣化対策等級3など) |
| 耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、損傷レベルの低減を図ること(耐震等級3など) |
| 省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること(断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6) |
| 維持管理・更新の容易性 | 設備配管について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること(戸建ては75㎡以上など) |
| 居住環境 | 地域の景観や居住環境の維持・向上に配慮されていること |
| 維持保全計画 | 定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること |
| 災害配慮 | 自然災害による被害の発生防止または軽減に配慮されていること |
これらの基準を満たすことで、長期優良住宅は構造的な強さはもちろん、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境、そして将来のメンテナンスまで考慮された、まさに「長く快適に住み続けられる家」となるのです。
【2025年最新】長期優良住宅で得られる経済的メリット

長期優良住宅の認定を受けると、さまざまな経済的メリットを享受できます。住宅ローン減税の拡充から各種税金の軽減、さらには返済不要の補助金まで、その恩恵は初期費用から入居後の維持費まで幅広く及びます。以下で、2025年最新の優遇制度について詳しく見ていきましょう。
住宅ローン減税による優遇措置
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して家を購入した際、年末のローン残高の0.7%を最大13年間、所得税や住民税から控除する制度です。長期優良住宅の最大の税制メリットは、この控除対象となる借入限度額が一般住宅よりも大幅に拡大されることにあります。
| 住宅の種類 | 2025年入居の借入限度額 | 控除期間 |
| 認定長期優良住宅 | 4,500万円(子育て世帯等※は5,000万円) | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円(子育て世帯等※は4,500万円) | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円(子育て世帯等※は4,000万円) | 13年 |
| その他の住宅 | 0円(2023年までの建築確認で2,000万円) | 10年 |
・※子育て世帯等の定義(「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)についても補足説明する。
たとえば、4,000万円の住宅ローンを組んだ場合、長期優良住宅なら全額が控除対象となりますが、省エネ基準適合住宅では3,000万円までしか対象になりません。この差額1,000万円分の控除機会を失うことになり、13年間で最大91万円もの差が生じる可能性があります。
各種税金における軽減措置
住宅を取得・保有する際には、さまざまな税金がかかりますが、長期優良住宅は不動産取得税、登録免許税、固定資産税のすべてで優遇措置を受けられます。
| 税の種類 | 優遇内容(長期優良住宅) | 一般住宅との比較 | 適用期限 |
| 不動産取得税 | 課税評価額から1,300万円を控除 | 一般住宅より100万円控除額が多い | 2026年3月31日までに新築 |
| 登録免許税(保存登記) | 税率0.1% | 一般住宅(0.15%)より低い | 2027年3月31日までに取得 |
| 固定資産税(戸建て) | 減税期間が5年間に延長 | 一般住宅(3年間)より2年間長い | 2026年3月31日までに新築 |
特に注目すべきは固定資産税の減税期間延長です。一般住宅では3年間しか受けられない半額措置が、長期優良住宅なら5年間に延長されます。仮に年間の固定資産税額が20万円の住宅なら、4年目と5年目で合計20万円(10万円×2年)の追加節税効果が得られることになり、入居後の長期的な家計負担を軽減する重要なメリットとなっています。
国の補助金制度による支援
長期優良住宅の建築にかかる費用負担を軽減するため、国は返済不要の補助金制度を設けています。2025年現在、利用可能な主な補助金として「子育てグリーン住宅支援事業」があります。
この制度は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、省エネ性能の高い住宅の取得を支援するものです。2025年度からは子育て世帯・若者夫婦世帯に限らず、すべての世帯が対象となりました。補助額は住宅の性能によって変動し、長期優良住宅なら80万円(建て替えの場合は100万円)の補助を受けられます。
もう一つの選択肢として「ZEH支援事業」もあります。こちらはZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を満たす住宅に対して、1戸あたり55万円(ZEH+なら90万円)の補助を行う制度です。ただし、「子育てグリーン住宅支援事業」との併用はできないため、自身の状況に応じて最適な制度を選択する必要があります。
参考:ZEH Web|2025年の経済産業省と環境省のZEH補助金について
金利や保険料などその他の優遇
税金や補助金以外にも、長期優良住宅にはさまざまな金銭的メリットがあります。
まず、住宅金融支援機構と民間金融機関が提供する【フラット35】Sを利用する場合、金利Aプランの対象となり、当初5年間、年0.5%もの金利引き下げを受けられます。さらに「維持保全型」との併用により、最大で当初5年間0.75%の引き下げも可能です。借入額が大きく返済期間が長い住宅ローンでは、わずかな金利差でも総返済額に大きな影響を与えるため、見逃せないメリットといえるでしょう。
地震保険料においても、認定基準の高い耐震性能により大幅な割引を受けられます。耐震等級2なら30%、耐震等級3なら50%の割引が適用されるため、年間の地震保険料が5万円の場合、耐震等級3なら年間2.5万円の節約となり、30年間では75万円もの差額が生じることになります。
さらに、親や祖父母から住宅購入のための資金援助を受ける際の贈与税においても優遇があります。住宅取得資金贈与の非課税限度額が、一般住宅の500万円に対し、長期優良住宅なら1,000万円まで拡大されるのです。仮に1,000万円の援助を受けた場合、一般住宅では500万円分に贈与税がかかりますが、長期優良住宅なら全額非課税となり、約150万円の節税効果があります。
なお、住宅ローンを利用せず自己資金(現金)で購入する場合は、「投資型減税」という制度も用意されています。性能強化費用相当額(上限650万円)の10%、最大65万円がその年の所得税から控除されます。ただし、この制度は住宅ローン減税との選択制となっており、併用はできない点に注意が必要です。
参考:住宅金融支援機構|家族構成と建て方に合わせた組合せで金利を引下げ!
参考:ZEH Web|2025年の経済産業省と環境省のZEH補助金について
長期優良住宅で考慮すべきデメリット

長期優良住宅には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。後悔のない家づくりのためには、これらの点もしっかりと理解した上で判断することが重要です。以下で、主なデメリットについて詳しく見ていきましょう。
建築費用や申請手続きに関するコスト
長期優良住宅の最も大きなデメリットとして、一般住宅に比べて初期費用が高くなる傾向があることが挙げられます。高い性能基準を満たすためには、断熱性能の高い窓や壁材、耐震性を高める構造部材、省エネ性能の優れた設備機器など、グレードの高い材料や設備を使用する必要があるためです。
建築費の増加に加えて、認定を受けるための申請費用も必要になります。申請・審査にかかる手数料は所管行政庁によって異なりますが、5〜6万円程度が一般的です。しかし、実際には申請書類の作成には専門知識が必要となるため、多くの場合、住宅会社や工務店に代行を依頼することになります。この代行手数料を含めると、合計で20〜30万円程度の費用がかかるのが相場となっています。
家づくりのスケジュールに関する注意点
長期優良住宅の認定申請は、必ず「工事着工前」に行わなければなりません。着工後に申請しても認定は受けられないため、この点は特に注意が必要です。
認定を受けるまでの審査期間は、通常の住宅よりも数週間から1ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。登録住宅性能評価機関での技術的審査を経て、所管行政庁での認定審査を受けるという2段階のプロセスを踏むためです。
また、高性能な住宅を建てるには、より丁寧な施工が求められます。断熱材の隙間なく施工したり、気密性を確保するための細かな作業が必要になったりするため、一般的な注文住宅よりも工期が長くなる傾向があります。子どもの入学や転勤など、入居希望日が明確に決まっている場合は、余裕を持ったスケジュール計画が不可欠となるでしょう。
入居後に求められる維持管理の義務
長期優良住宅は、建てて終わりではありません。その性能を長期間維持するために、計画的なメンテナンスが義務付けられているのです。
認定申請時に提出した「維持保全計画」に基づき、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について、少なくとも10年ごとに点検を実施する必要があります。さらに、大きな地震や台風の後には臨時的な点検も求められます。
これらの点検や修繕の履歴は、きちんと記録として作成・保存しなければなりません。維持保全を怠った場合、最悪のケースでは認定が取り消される可能性もあります。定期的なメンテナンスには費用もかかるため、入居後の維持管理コストも考慮に入れておく必要があるでしょう。
長期優良住宅は本当に必要?自分に合うかの判断ポイント

長期優良住宅にはメリットもデメリットもあります。では、自分にとって本当に必要なのでしょうか。ここでは、住宅性能と資産価値、ライフプラン、そしてコストの観点から、長期優良住宅を選ぶべきかどうかの判断ポイントを整理していきます。
住宅性能と資産価値から考える
長期優良住宅の必要性を判断する上で、まず考えるべきは住宅そのものの価値です。認定基準を満たすことで得られる高い耐震性は、地震大国日本において家族の命と財産を守る重要な要素となります。また、優れた断熱性能は、夏の暑さや冬の寒さから家族を守り、快適で健康的な暮らしを実現してくれるでしょう。
将来的な資産価値の面でも、長期優良住宅には大きなメリットがあります。国が定めた厳しい基準をクリアした高品質な住宅であることが公的に証明されているため、中古住宅市場でも評価されやすいのです。一般的な住宅は築年数とともに価値が下がっていきますが、長期優良住宅なら適切なメンテナンスを行うことで、資産価値を長期間維持できる可能性が高くなります。
ライフプランと住まい方から考える
長期優良住宅のメリットを最大限に享受できるかどうかは、自身のライフプランや住まいに対する価値観によって大きく左右されます。
一つの家に長く住み続けることを想定している人にとっては、長期優良住宅は理想的な選択肢といえるでしょう。初期費用は高くなりますが、税制優遇や光熱費の削減効果が長期間にわたって続くため、トータルコストで見れば一般住宅よりもお得になる可能性が高いです。
一方で、転勤が多い仕事に就いている人や、将来的に住み替えを考えている人にとっては、初期コストの負担が重くなるかもしれません。せっかく高い費用をかけて建てた家でも、数年で手放すことになれば、経済的メリットを十分に享受できない可能性があります。
また、定期的なメンテナンスを「大切な家を守るための必要な投資」と前向きに捉えられるか、それとも「面倒な義務」と感じてしまうか、この価値観の違いも重要な判断材料となるでしょう。
コストと経済的リターンのバランスから考える
長期優良住宅を選ぶかどうかの最終的な判断では、初期コストの増加分を将来の経済的リターンで回収できるかという視点が欠かせません。
補助金や各種税制優遇を合わせると、トータルで数百万円規模の優遇を受けられる可能性があります。しかし、実際に得られる減税額は、住宅ローンの借入額や年収、家族構成などによって大きく変わってきます。たとえば、住宅ローン減税は借入額が大きく、所得税を多く払っている人ほどメリットが大きくなる仕組みです。
さらに、高い断熱性能による光熱費の削減効果も見逃せません。一般的な住宅と比べて年間10万円以上の光熱費削減が可能なケースもあり、30年間では300万円以上の差になることもあります。
建築を依頼する住宅会社には、初期費用の増加分と、補助金・税制優遇による減額分、さらに将来の光熱費やメンテナンス費用まで含めたトータルコストのシミュレーションを依頼することをおすすめします。具体的な数字を見ることで、長期優良住宅が自分にとって本当にお得なのか、納得のいく判断ができるはずです。
鳥取・島根の注文住宅なら長期優良住宅が標準仕様のトコスホームへ
ここまで長期優良住宅のメリット・デメリットを詳しく見てきました。高い初期費用というハードルはあるものの、税制優遇や補助金、そして何より安心・快適に長く住み続けられる価値を考えれば、多くの方にとって魅力的な選択肢といえるでしょう。
鳥取・島根エリアで長期優良住宅をご検討中の方には、トコスホームがおすすめです。トコスホームの家は、長期優良住宅の性能基準である耐震等級3、断熱等性能等級5以上などを標準仕様でクリアしています。つまり、特別な追加費用をかけることなく、国が認める高性能な住まいを手に入れることができるのです。
特筆すべきは、山陰の厳しい気候風土を知り尽くした「山陰スタンダード」仕様です。国の基準を上回る高気密・高断熱性能(UA値0.34、C値0.5±0.2)により、雨や雪が多く、夏冬の寒暖差が激しい山陰でも、光熱費を抑えながら一年中快適な暮らしを実現します。
建てた後の安心も、トコスホームの大きな強みです。最長60年という業界トップクラスの長期保証により、長期優良住宅に求められる維持管理も安心してお任せいただけます。定期点検やメンテナンスのご相談はもちろん、住まいに関するあらゆるお悩みに寄り添い続けます。
長期優良住宅で理想の暮らしを実現したい方は、ぜひ一度トコスホームにご相談ください。土地探しから資金計画、補助金申請のサポートまで、家づくりのすべてをワンストップでお手伝いいたします。
関連記事:家づくりは何から始める?注文住宅を建てる流れや期間をわかりやすく解説
関連記事:3LDK平屋の間取りは?価格相場や建てる際の注意点も解説