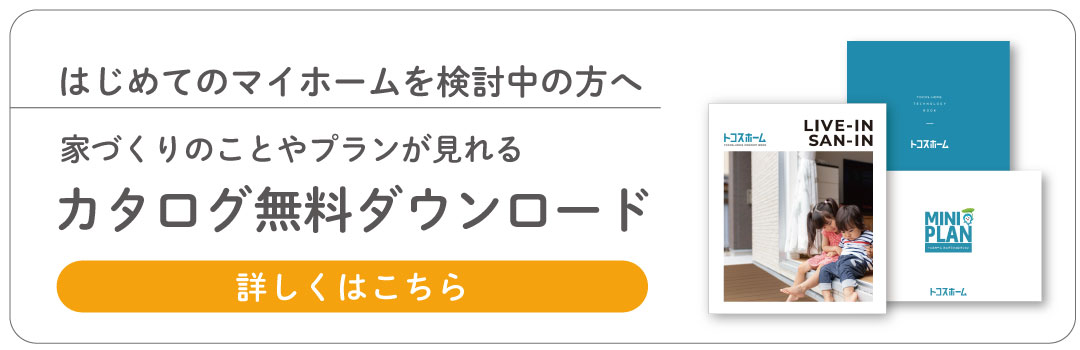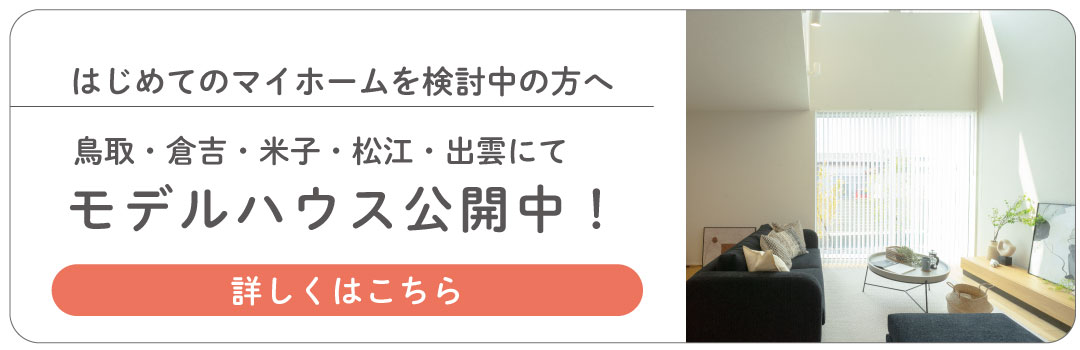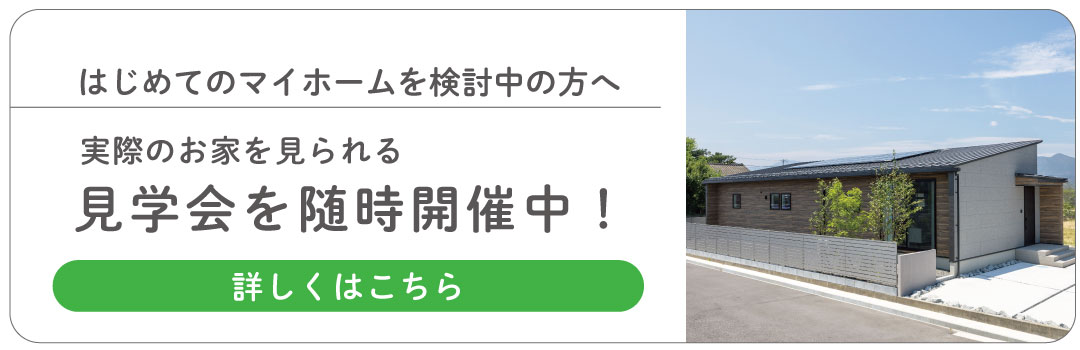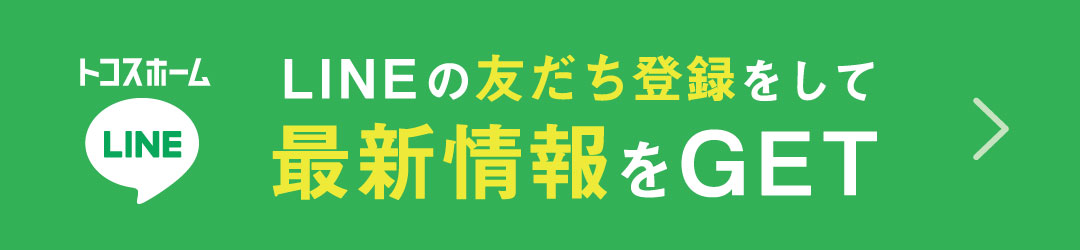断熱等性能等級とは?住宅の等級による違いや調べ方を解説
 目次
目次
これから家づくりを始める人や注文住宅を検討している人の中には、「断熱等性能等級」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。断熱等性能等級とは、住宅の断熱性能をどれだけ備えているかを示す指標です。
本記事では、断熱等性能等級の基本的な仕組みから最新の制度改正まで、わかりやすく解説していきます。2022年に新設された上位等級の詳細や、2025年以降の義務化に向けた準備、さらには断熱性能を確認する具体的な方法まで、幅広く網羅しました。この記事を読んで、ご自身の住宅に必要な断熱性能を正しく判断し、より快適で経済的な住まいづくりに向けた一歩を踏み出しましょう。
断熱等性能等級とは

断熱等性能等級とは、2000年に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められた、住宅の断熱性能を示す指標です。住宅における熱の出入りを防ぐ性能を数値化し、国が定めた基準に基づいて評価しています。
この等級は1から7までの7段階で構成されており、数字が大きければ大きいほど熱の出入りが少ない、つまり断熱性能が高いことを意味します。最も低い等級1は昭和55年基準未満の性能を示し、最高等級の7は暖冷房にかかるエネルギー消費量を約40%削減できるレベルの高い断熱性能を有しています。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、日本においても環境問題への関心が高まっていることが背景にあり、住宅分野でも脱炭素化への取り組みが加速しています。政府は住宅の断熱性能向上を通じて、家庭部門からの二酸化炭素排出量削減を目指しており、断熱等性能等級はその実現に向けた重要な指標として位置づけられています。
住宅性能表示制度における断熱等性能等級の位置づけ
断熱等性能等級は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の中にある、住宅性能表示制度に定められた項目の一つです。具体的には、住宅性能表示制度の10の評価項目のうち、「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」の評価項目に該当します。
この評価では、外皮(外壁、窓など)の断熱性能、冷房期に日射を遮蔽する対策、結露の発生を抑制するための対策など、住宅外皮の断熱性能について評価します。外皮とは、屋根、天井、壁、床、窓、ドアなど住宅の内外の境界になる部分のことを指し、これらの部位における熱の出入りをいかに抑えるかが評価の対象となります。
住宅性能表示制度を活用することで、住宅購入者は客観的な性能評価を確認でき、住宅の品質を比較検討しやすくなります。評価書の取得は、設計段階で交付される「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階で交付される「建設住宅性能評価書」の2種類があり、国土交通大臣に登録された第三者評価機関による審査を受けることで取得できます。
2022年新設の等級5・6・7がもたらす変化
断熱等級は2022年3月までは4が最高等級でしたが、2022年4月に等級5が、同年10月に等級6と7が新設されました。これは実に23年ぶりの上位等級新設という画期的な制度改正であり、日本の住宅における断熱性能の新たな基準を示すものとなりました。
各等級のエネルギー消費量削減率は以下のとおりです。
| 等級 | エネルギー消費量削減率 |
| 等級7 | 約40%削減 |
| 等級6 | 約30%削減 |
| 等級5 | 約20%削減(ZEH水準と同等) |
断熱等級が向上することで、室温や体感温度にも大きな変化が見られます。たとえば、従来の等級4の住宅では冬の明け方に室温が8℃まで低下することがありましたが、等級6になると暖房に必要なエネルギーが半分以下で済むようになり、明け方の極端な寒さが感じにくくなります。さらに等級7では、部分的な暖房でも明け方の室温が15℃を下回る可能性が非常に低くなります。また、室温が同じ20℃であっても、断熱性の高い住宅では壁や床からの輻射熱の影響で体感温度が19℃に感じられるのに対し、断熱性の低い住宅では15℃と大きく異なることが示されています。これは、高断熱化によって、必要以上に冷暖房設備を使用することなく快適に過ごせることを意味します。
2025年以降の義務化に向けた準備と対策
2025年以降に新築する住宅では、断熱等級4以上、2030年には等級5以上の義務化が決まっています。これにより、2025年度以降は全ての新築住宅に等級4以上が義務化されるため、2022年3月まで最高等級だった等級4は実質、最低等級になることが予定されています。
さらに2030年には省エネ基準の水準が引き上げられ、断熱等級5が最低等級になる予定です。これは現在のZEH水準が標準的な性能として求められることを意味しており、住宅業界にとって大きな転換点となります。
各断熱等級の性能基準と特徴

断熱等級は、「UA値(外皮平均熱貫流率)」と「ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)」という2つの数値で決定されます。これらの数値は、いずれも住宅の外皮性能を構成する重要な指標です。日本の気候条件は地域によって大きく異なるため、国土交通省は全国を8つの地域区分に分け、それぞれの地域区分に応じて達成すべきUA値とηAC値の基準値を定めています。これにより、地域ごとの気候に合わせた適切な断熱性能が求められることになります。
等級別の性能数値(UA値・ηAC値)と地域区分
UA値(外皮平均熱貫流率)は、室内と外気の熱の出入りのしやすさを示す指標です。この値は、建物内外の温度差が1℃のときに、建物内部から外部へ逃げる単位時間あたりの熱量(換気による熱損失を除く)を、外皮の総面積で割ることで算出されます。したがって、UA値が小さいほど熱が逃げにくく、住宅の断熱性が高いことを示します。
ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)は、太陽からの日射熱が室内にどれだけ入りやすいかを示す指標です。この値は、単位日射強度あたりの日射によって建物内部で取得される熱量を冷房期間で平均し、外皮面積で割ることで算出されます。ηAC値が小さいほど日射熱の侵入が少なく、遮熱性能が高いことを意味し、夏季の一次エネルギー消費量を削減する上で重要です。
以下に、8つの地域区分別のUA値とηAC値の基準値をまとめました。
地域区分と基準値の対応表
| 地域区分 | 主な該当地域 | 等級7 | 等級6 | 等級5 |
| 1・2地域 | 北海道等の寒冷地 | UA値:0.20
ηAC値:― |
UA値:0.28
ηAC値:― |
UA値:0.40
ηAC値:― |
| 3地域 | 東北・北関東の一部 | UA値:0.20
ηAC値:― |
UA値:0.28
ηAC値:― |
UA値:0.50
ηAC値:― |
| 4地域 | 関東・東海の一部 | UA値:0.23
ηAC値:― |
UA値:0.34
ηAC値:― |
UA値:0.60
ηAC値:― |
| 5地域 | 関東・東海・近畿の多く | UA値:0.26
ηAC値:3.0 |
UA値:0.46
ηAC値:3.0 |
UA値:0.60
ηAC値:3.0 |
| 6地域 | 近畿・中国・四国の一部 | UA値:0.26
ηAC値:2.8 |
UA値:0.46
ηAC値:2.8 |
UA値:0.60
ηAC値:2.8 |
| 7地域 | 九州・四国の一部 | UA値:0.26
ηAC値:2.7 |
UA値:0.46
ηAC値:2.7 |
UA値:0.60
ηAC値:2.7 |
| 8地域 | 沖縄等の温暖地 | UA値:―
ηAC値:― |
UA値:―
ηAC値:5.1 |
UA値:―
ηAC値:6.7 |
(UA値 [W/(㎡・K)]、ηAC値 [-])
参考:国土交通省|住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設
各地域区分は、その地域の気候特性を考慮して設定されています。たとえば、1・2地域のような寒冷地では、より低いUA値が求められ、高い断熱性能が必要です。一方、5・6・7地域のような温暖な地域では、夏季の日射遮蔽性能を示すηAC値も重視されます。
省エネ基準・ZEH水準・HEAT20との関係性
断熱等級4は「平成28年 省エネ基準」と同等であり、これは1999年に制定された「次世代省エネ基準」に相当します。一方、等級5は「ZEH水準」の断熱基準と同等となっており、より高い省エネ性能が求められています。
HEAT20(一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会)は、「豊かなくらし」実現のために、理想的な室内の温熱環境を目指して考案されました。ZEH水準よりも厳しい、G1・G2・G3の3段階の住宅外皮水準を制定しています。断熱等級との関係では、等級6は「HEAT20」G2と概ね同等、等級7は「HEAT20」G3と概ね同等となっていますが、5地域の基準値はHEAT20の断熱性能水準とは異なる点に注意が必要です。
ZEH(Net Zero Energy House)は、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅を指します。ZEH実現に必要な要件は以下のとおりです。
- 断熱等性能等級5以上の外皮性能
- 高効率な設備システムの導入(エコキュート、LED照明など)
- 太陽光発電などの再生可能エネルギー設備の設置
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入
- 一次エネルギー消費量を基準から20%以上削減(再エネ除く)
- 創エネを含めて基準一次エネルギー消費量から100%以上削減
断熱等級の確認方法と向上のポイント

2021年の国土交通省の資料によると、日本の既存住宅において、その約90%が断熱等級3以下といわれています。多くの住宅が現在の基準から見ると不十分な断熱性能にとどまっており、エネルギー効率や快適性の面で改善の余地が大きいことを示しています。
断熱等級を向上させることで、さまざまな健康改善効果が期待できます。高断熱化により、のどの痛み、手足の冷え、気管支喘息、アレルギー性皮膚炎等の症状が改善される傾向にあります。また、室内の温度差が小さくなることで、ヒートショックのリスクを抑えられます。
経済面では、外気の温度の影響を受けにくく室内環境を一定に保ちやすくなるため、エアコンの設定温度を弱めにしても十分な暖かさ・涼しさを感じられるようになり、これにより節電・節約につながるでしょう。さらに、都道府県や市町村によっては、断熱対策を施した住宅を建てることで補助金を受けられます。
新築・中古住宅における断熱等級の調べ方
新築住宅の場合、300㎡未満の新築住宅であれば、建築士から建築主(施主)へ省エネ基準(断熱等級4)の適否を説明するよう義務付けられています。この説明義務により、建築主は自身の住宅がどの程度の断熱性能を有するかを把握できるようになりました。省エネ基準を超える断熱性能(断熱等級5以上)は住宅性能表示制度を利用することで確認可能です。
分譲住宅や中古住宅などの竣工後の建築物の場合は、不動産会社などに相談して住宅性能評価書を取得することで把握できるケースがあります。ただし、すべての物件で評価書が取得されているわけではないため、取得されていない場合は、新たに既存住宅の性能評価を受ける必要があります。
マンションと戸建てそれぞれの断熱等級確認時の注意点は以下のとおりです。
- マンションの場合:共用部分との関係で断熱改修に制限がある場合があるため、管理規約の確認が必要
- 戸建ての場合:建築年代により使用されている断熱材の種類や施工方法が異なるため、図面だけでなく現地確認も重要
- 両方に共通:リフォーム履歴がある場合は、断熱改修の有無と内容を確認することが必要
- 評価書がない場合:専門業者による断熱診断を受けることで、現状の性能を把握可能
断熱性能を高めるための窓・サッシの選び方
住宅において、窓などの開口部は熱の出入りが最も多い場所となっています。夏は窓から入る日射熱が全体の約70%、冬は窓から逃げる熱が全体の約50%を占めるといわれており、断熱性能向上の鍵を握っています。
断熱等級を上げることで実際どのくらい費用が高くなるのかは、家の広さやどの地域区分に属するのか、家を建てるエリアが防火地域などに区分されているのかによっても違います。さらに選ぶ断熱材や窓・サッシの種類(アルミ・樹脂など)によっても違ってきます。
等級6以上を実現するためにはまず、ガラスは単板ガラスから複層ガラス、さらにはトリプルガラスへの変更が効果的です。複層ガラスの中空層にアルゴンガスなどを封入したものや、Low-E(低放射)コーティングを施したものを選ぶことで、断熱性能が大幅に向上します。
サッシ部分については、熱伝導率の高いアルミサッシから、樹脂サッシやアルミ樹脂複合サッシへの変更が重要です。樹脂サッシは熱伝導率がアルミの約1/1000と非常に低く、結露の発生も抑制できます。さらに、窓の開閉方式も断熱性能に影響し、引き違い窓よりも、はめ殺し窓や内開き窓の方が気密性が高くなります。
注文住宅を建てるならトコスホームへ
住宅の断熱性能は、快適な暮らしと省エネルギーを実現するための重要な要素です。2025年以降の義務化に向けて、断熱等級4以上が最低基準となり、将来的には等級5、さらにはそれ以上の性能が求められる時代が到来します。高い断熱性能は、健康的な室内環境の実現、ヒートショックリスクの軽減、そして光熱費の大幅な削減につながる投資といえるでしょう。
トコスホームでは、山陰エリアの気候特性を熟知し、東京大学・前研究室との共同研究に基づいた「山陰スタンダード」を確立しています。断熱等性能等級6相当のUA値0.34を標準仕様とし、国の基準を大きく上回る高性能住宅を、想定以内の予算で実現します。高気密・高断熱により光熱費を従来の約半分に抑え、60年間のランニングコストまでデザインした家づくりを提供。鳥取・島根で着工数No.1の実績を持つアート建工グループの一員として、土地探しから資金計画、設計・施工まで一貫してサポート。最長60年保証という安心とともに、世代を超えて快適に暮らせる住まいをご提案いたします。