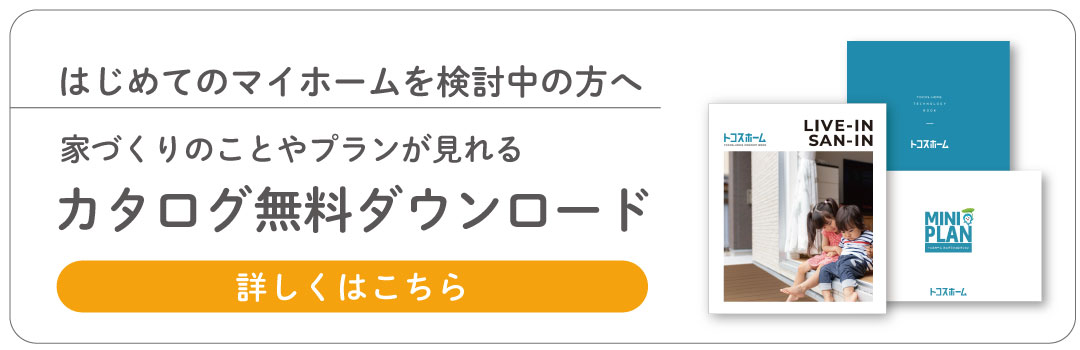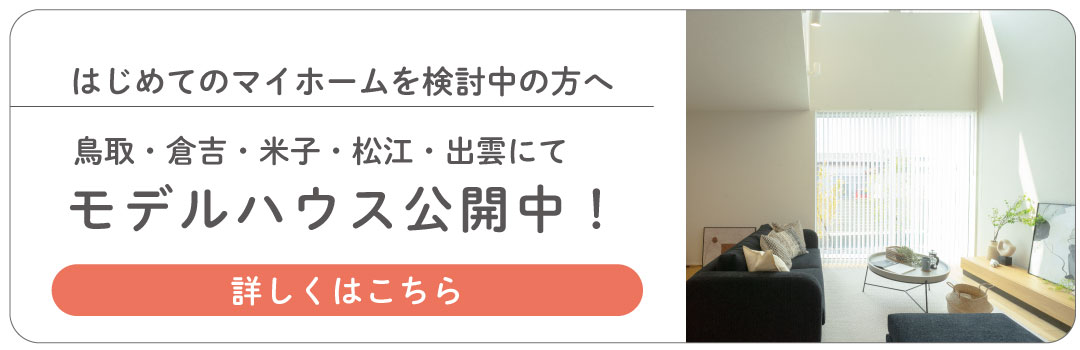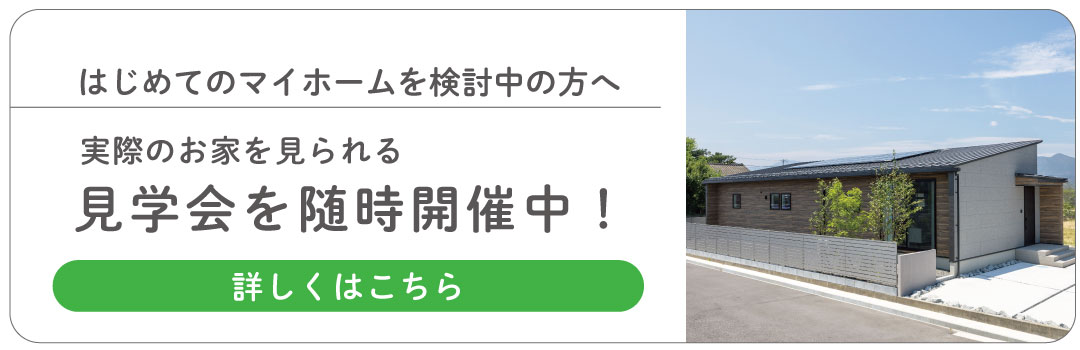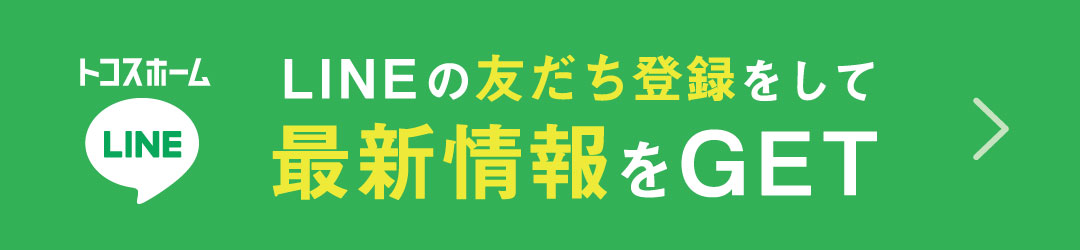家づくりの流れを徹底解説!期間や進め方をわかりやすく紹介

目次
「家づくりって何から始めればいいの?」「どのくらいの期間がかかるの?」など、初めての家づくりは、誰もが不安や戸惑いを感じるものです。この記事では、家づくりの全体的な流れを準備段階から入居後まで、ステップごとにわかりやすく解説していきます。
家づくりは人生の大きな節目となる大切なプロジェクトです。情報収集から始まり、資金計画、土地探し、設計、施工まで、多くのプロセスを経て理想の住まいが完成します。一般的に土地探しから完成まで約1年かかりますが、この期間を有効に使い、後悔のない家づくりを実現するためのポイントをお伝えしていきます。
【準備編】後悔しない家づくりの第一歩

家づくりを始めるにあたって、いきなり土地探しや建築会社選びに飛びつくのは避けたいところです。まずは準備段階として、情報収集、資金計画、会社選びという3つの重要なステップを踏むことが大切になります。
この初期段階をしっかりと行うことで、その後の土地探しや設計打ち合わせがスムーズに進みます。逆に準備が不十分だと、予算オーバーや希望と違う家になってしまうなど、さまざまな問題が生じる可能性があります。
丁寧な準備は、後のプロセスでの失敗や後悔を防ぐ最良の方法といえるでしょう。それでは、準備段階の具体的な進め方を見ていきましょう。
理想の暮らしをイメージする情報収集のコツ
家づくりの第一歩は、理想の暮らしをイメージすることから始まります。SNSやWebサイト、住宅展示場など、現在は情報源が豊富にありますが、それぞれに特徴があります。
InstagramやPinterestでは、実際に建てた人の生活風景や内装のアイデアを視覚的に収集できます。一方、住宅展示場では実際の空間を体感でき、最新の設備や間取りのトレンドを確認できるメリットがあります。ただし、展示場の家は豪華仕様になっていることが多いため、予算との兼ね合いを考慮する必要があるでしょう。
情報を集めたら、家族全員で理想の暮らしについて話し合いましょう。「リビングからキッチン全体を見渡したい」「子ども部屋は将来仕切れるようにしたい」など、具体的な要望をリストアップします。現在の住まいの不満点を挙げることも、新しい家で改善したいポイントが明確になるため有効です。
要望が出揃ったら、優先順位をつけることが重要になります。すべての希望を叶えることは予算的に難しいことが多いため、「絶対に譲れない条件」「あったら嬉しい条件」「なくても構わない条件」に分類しておくとよいでしょう。
イメージがなかなか固まらない場合は、住宅イベントや相談会への参加がおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、漠然としたイメージが具体的な形になっていきます。
無理のない予算を立てる資金計画のポイント
家づくりで最も重要なのが資金計画です。まず、家づくりに使える総予算を把握することから始めましょう。総予算は「自己資金」「住宅ローン借入額」「親からの援助」の3つを合計したものになります。
自己資金については、すべてを頭金に充てるのではなく、万が一のための生活防衛資金を残しておくことが大切です。住宅ローンの借入額は、年収の5〜7倍が目安とされていますが、月々の返済額が手取り収入の25%以内に収まるよう計画することが重要です。
建物本体の費用以外にも、さまざまな諸費用がかかることを忘れてはいけません。以下の表を参考に、物件価格の5〜10%程度を諸費用として見込んでおきましょう。
【諸費用の内訳】
| 費用項目 | 内容・説明 |
| 登記費用 | 土地や建物の所有権を登記するための費用。司法書士への報酬も含まれる。 |
| 税金 | 不動産取得税、登録免許税(登記時)、契約書に貼る印紙税など。 |
| 住宅ローン関連費用 | 金融機関に支払う事務手数料、保証料、団体信用生命保険料など。 |
| 付帯工事費 | 外構工事、地盤改良工事、上下水道・ガスの引き込み工事など、建物本体以外の工事費用。 |
| 火災保険料・地震保険料 | 火災や自然災害に備えるための保険料。住宅ローン契約の条件となる場合が多い。 |
| その他 | 地鎮祭や上棟式にかかる費用、引っ越し費用、家具・家電購入費用など。 |
また、住宅ローン減税をはじめとした各種制度を活用することで、実質的な負担を軽減できます。詳しくは以下の記事もご参照ください。
関連記事:【2025年最新】長期優良住宅の補助金・住宅ローン減税・税制優遇を解説
パートナーとなる建築会社の選定方法
理想の家づくりを実現するためには、信頼できるパートナーとなる建築会社選びが欠かせません。依頼先には大きく分けてハウスメーカー、工務店、設計事務所の3種類があり、それぞれに特徴があります。
【建築会社の種類別メリット・デメリット】
| 依頼先 | メリット | デメリット |
| ハウスメーカー | ・品質が安定している
・長期保証やアフターサービスが充実 ・住宅展示場で実物を確認できる |
・設計の自由度が低い場合がある
・広告宣伝費などが上乗せされ高額になりがち ・仕様変更などの柔軟な対応が難しい |
| 工務店 | ・設計の自由度が高く、こだわりを反映しやすい
・地域特性を熟知した提案が期待できる ・比較的コストを抑えやすい |
・会社によって技術力や品質にばらつきがある
・完成イメージを掴みにくい ・倒産のリスクがハウスメーカーより高い |
| 設計事務所 | ・デザイン性が高く、オリジナリティのある家づくりが可能
・複雑な土地や要望にも対応しやすい ・施主の代理として工事を監理してくれる |
・設計料や監理料が別途必要で、総額が高額になる
・工期が長くなる傾向がある |
信頼できるパートナーを見極めるためのチェックポイントは以下のとおりです。
- 会社の信頼度:施工実績、財務状況、研究開発への取り組みなどを総合的に判断
- 実例見学の重要性:実際に建てた住宅を見学し、暮らしぶりやインテリアを確認
- アフターサポートの内容:保証期間、定期点検の頻度、対応窓口の一本化など
- 的確なアドバイスの有無:法律・税務・資金計画まで幅広くサポートできるか
工務店選びについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事:工務店のデメリットは?依頼時の注意点やメリット・ハウスメーカーとの違いも解説
【実践編】家づくりの具体的な進め方

準備が整ったら、いよいよ家づくりの実践段階に入ります。ここからは土地探し、詳細打ち合わせ、契約手続き、そして着工という4つの重要なステップを経て、夢のマイホームが形になっていきます。
家づくりの全体像を把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、安心して進められるようになります。一般的に土地探しから着工まで6〜8ヶ月程度かかりますが、土地の条件や打ち合わせの進捗によって期間は前後します。
スケジュール管理をしっかり行いながら、一つひとつのステップを着実に進めていくことが成功への近道となるでしょう。それでは、具体的な進め方を詳しく見ていきましょう。
理想の住まいを建てるための土地探しの進め方
建築会社が決まってから土地探しを始めるのがおすすめです。建築のプロの視点から土地を評価してもらえるため、希望の家が建てられるかどうかを事前に確認できます。また、土地と建物の総額を把握しながら探せるため、予算オーバーを防ぐことができるでしょう。
土地選びでは、法的制限の確認が欠かせません。用途地域によって建築できる建物の種類が決まっており、建ぺい率や容積率によって建物の規模が制限されます。たとえば、第一種低層住居専用地域では、建物の高さが10mまたは12mに制限されるため、3階建ての計画がある場合は注意が必要です。
生活環境のチェックも重要なポイントです。最寄り駅までの距離、通勤・通学ルート、スーパーや病院などの生活施設の充実度を確認しましょう。子育て世帯であれば学区も重要な判断材料となります。また、ハザードマップで洪水や土砂災害のリスクも必ず確認してください。
気に入った土地が見つかったら、買付証明書を提出して購入の意思表示をします。この時点では金銭の支払いは発生しませんが、他の購入希望者より優先的に交渉を進められるようになります。その後、重要事項説明を受け、内容に納得できたら売買契約を締結します。契約時には手付金として土地価格の5〜10%程度を現金で支払う必要があるため、事前に準備しておきましょう。
間取りや仕様を決める詳細な打ち合わせの流れ
土地が決まったら、敷地調査と地盤調査を実施します。敷地調査では法的制限や周辺環境を詳しく調べ、地盤調査では建物を安全に支えられる地盤かどうかを確認します。地盤が弱い場合は改良工事が必要となり、数十万円から100万円程度の追加費用がかかることもあるため、事前の調査が重要です。
調査結果を踏まえて、いよいよ間取りの打ち合わせが始まります。家族の要望を効果的に伝えるためには、実際の生活をシミュレーションすることがポイントです。朝起きてから夜寝るまでの動線を考え、洗濯物を干す場所から収納までの移動、キッチンから洗面所への家事動線など、具体的にイメージしながら検討しましょう。
決めるべき項目は間取りだけにとどまりません。外壁材や屋根材、断熱性能、窓の配置、内装材、キッチンや浴室などの設備機器、照明計画、コンセントの位置、外構計画など、多岐にわたります。これらの打ち合わせには通常3〜4ヶ月程度かかるため、じっくりと時間をかけて納得のいくまで検討することが大切です。
子育てしやすい間取りのアイデアについては、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:子育てしやすい家の間取りは?おすすめの住宅アイデア例を紹介
各種契約と住宅ローン手続きの注意点
間取りや仕様が固まったら、住宅ローンの手続きと各種契約に進みます。住宅ローンには事前審査と本申込みの2段階があり、それぞれ異なる役割があります。
事前審査は、年収や職業などの基本情報から融資の可否を簡易的に判断するもので、通常1週間程度で結果が出ます。この段階で複数の金融機関に申し込み、条件を比較検討することが賢明です。本申込みは、詳細な書類を提出して正式な審査を受けるもので、土地と建物の契約が決まってから行います。
工事請負契約を締結する際は、以下の書類をしっかりと確認してください。
- 工事請負契約書:工事内容、金額、工期、支払い条件などが記載
- 設計書:平面図、立面図、断面図など建物の詳細な図面
- 仕様書:使用する材料や設備の品番、仕様が明記
- 見積書:工事費用の内訳が項目ごとに記載
契約内容の確認は非常に重要です。専門用語がわからない場合は遠慮なく質問し、納得できるまで説明を受けましょう。契約後の変更は追加費用や工期延長につながる可能性が高いため、契約前の十分な確認が欠かせません。
建築確認申請は、計画している建物が建築基準法に適合しているかを審査する手続きです。申請が承認されると「建築確認済証」が交付され、これをもって着工が可能となります。
工事開始から建物完成までの期間と確認事項
すべての手続きが完了したら、いよいよ着工です。一般的な木造住宅の場合、着工から完成まで約4〜6ヶ月かかります。工事は基礎工事から始まり、上棟(建物の骨組みが完成)、屋根・外壁工事、内装工事、設備工事という流れで進んでいきます。
着工前には地鎮祭を行うことが一般的です。これは土地の神様に工事の安全を祈願する儀式で、施主、建築会社、工事関係者が参加します。地鎮祭の日程に合わせて、近隣住民への挨拶回りも済ませておきましょう。工事中は騒音や工事車両の出入りでご迷惑をおかけすることを事前に伝え、理解を得ておくことが、入居後の良好な関係づくりにつながります。
工事中は定期的に現場を訪れることをおすすめします。基礎配筋の確認、上棟時の構造チェック、断熱材の施工状況、内装工事前の配線・配管位置の最終確認など、重要なタイミングで立ち会うことで、施工ミスを防ぐことができます。特にコンセントやスイッチの位置は、実際に現場で確認することで使い勝手の良い配置にできるでしょう。
不明な点や気になることがあれば、現場監督や工事責任者に遠慮なく質問してください。「こんなはずじゃなかった」という後悔を防ぐためにも、疑問は都度解消していくことが重要です。
【完成・入居後】理想の暮らしを維持する流れ
 待ちに待った住宅が完成し、新生活がスタートする時がやってきました。しかし、家づくりは建物が完成して終わりではありません。引き渡しを受けた後も、快適な暮らしを長く続けるために重要なポイントがいくつかあります。
待ちに待った住宅が完成し、新生活がスタートする時がやってきました。しかし、家づくりは建物が完成して終わりではありません。引き渡しを受けた後も、快適な暮らしを長く続けるために重要なポイントがいくつかあります。
引き渡し時の最終チェックをしっかり行い、入居後は適切なメンテナンスを続けることで、住宅の性能を長期間維持できます。家は建てて終わりではなく、住みながら手入れをして育てていくものだという視点を持つことが大切です。
ここでは、竣工から入居後のメンテナンスまで、理想の暮らしを維持するための具体的な流れを見ていきましょう。
入居前に実施する竣工立ち合いのチェック項目
引き渡し前に行う竣工立ち合い(内覧会)は、完成した住宅が契約どおりに仕上がっているかを確認する最後のチャンスです。建築会社の担当者と一緒に、建物の内外を丁寧にチェックしていきます。この段階で見つけた不具合は、引き渡し前に無償で補修してもらえるため、遠慮せずに指摘することが重要です。
チェックすべき主な項目は以下のとおりです。
- 外壁や内壁の傷、汚れ、塗装ムラ
- 床の傷、きしみ、段差
- 建具(ドア、窓、襖など)の開閉状態、建て付け
- 水回り設備(キッチン、浴室、トイレ)の動作確認
- 電気設備(照明、コンセント、スイッチ)の位置と動作
- 給排水の水漏れ、排水の流れ
- 換気扇、エアコンなどの動作音
- 外構の仕上がり状態
細かい部分まで確認するため、2〜3時間程度の時間を確保しておきましょう。気になる点はその場で写真を撮り、補修箇所リストを作成してもらいます。補修が完了したら再度確認を行い、問題がなければ引渡確認書にサインをして鍵と保証書を受け取ります。
入居後の暮らしを支える定期点検とアフターサービス
快適な住環境を長期間維持するためには、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。多くの建築会社では、引き渡し後も定期点検サービスを提供しており、専門スタッフが住宅の状態をチェックしてくれます。
一般的な定期点検のスケジュールは次のとおりです。
- 6ヶ月点検:初期不良の確認、建具の調整など
- 1年点検:四季を通じた不具合の確認、設備機器の点検
- 2年点検:構造材の状態確認、防水性能のチェック
- 5年点検:外壁、屋根などの劣化状況確認
- 10年点検:大規模な点検、必要に応じた有償メンテナンスの提案
点検時期や内容は建築会社によって異なるため、契約前に必ず確認しておきましょう。保証内容についても、構造躯体、雨水の浸入、設備機器など、部位ごとに保証期間が異なることが一般的です。
長期優良住宅の認定を受けている場合は、より手厚い保証や税制優遇が受けられます。詳しくは以下の記事をご参照ください。
日常的なメンテナンスも重要です。定期的な清掃、換気、点検を行うことで、住宅の劣化を防ぎ、快適な住環境を保つことができます。特に水回りの清掃や外壁の汚れチェックは、早期発見・早期対処により大きなトラブルを防ぐことにつながります。
関連記事:長期優良住宅のメリットは?デメリットや申請方法・ポイントを解説
鳥取・島根の家づくりならトコスホームにご相談を
本記事では、家づくりの流れを準備段階から入居後のメンテナンスまで詳しく解説してきました。情報収集から始まり、資金計画、建築会社選び、土地探し、設計・契約、工事、そして入居後の生活まで、家づくりは長い道のりですが、一つひとつのステップを丁寧に進めることで、理想の住まいを実現することができます。
トコスホームは、山陰の気候風土を熟知した地域密着型の住宅会社として、「山陰スタンダード」の家づくりを提供しています。夏は高温多湿、冬は積雪もある山陰地方の厳しい環境に対応した、高気密・高断熱の快適な住まいをご提案します。
土地探しから資金計画、設計、施工、そしてアフターサポートまで、すべてをワンストップで対応できることが私たちの強みです。お客様の理想の暮らしを実現するため、経験豊富なスタッフが親身になってサポートいたします。
また、トコスホームの住宅は全棟が耐震等級3(最高等級)を取得し、UA値0.34以下の高い断熱性能を標準仕様としています。さらに最長60年の長期保証により、世代を超えて安心して暮らせる住まいをお約束します。
家づくりでお悩みの方は、ぜひトコスホームにご相談ください。あなたの夢を形にするお手伝いをさせていただきます。