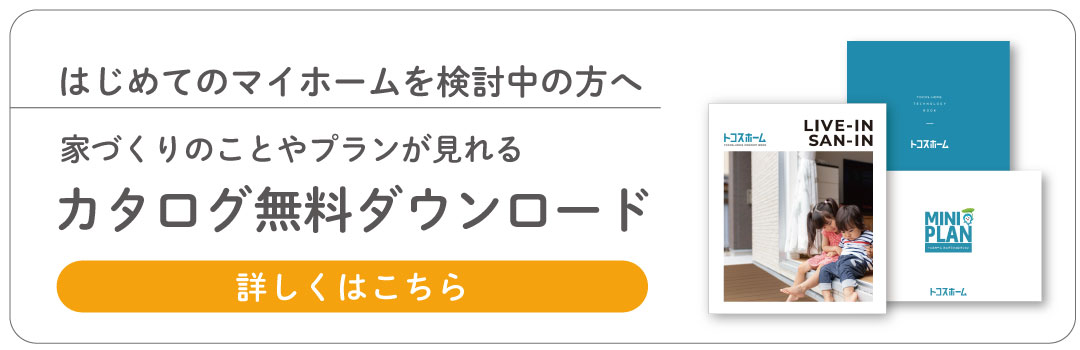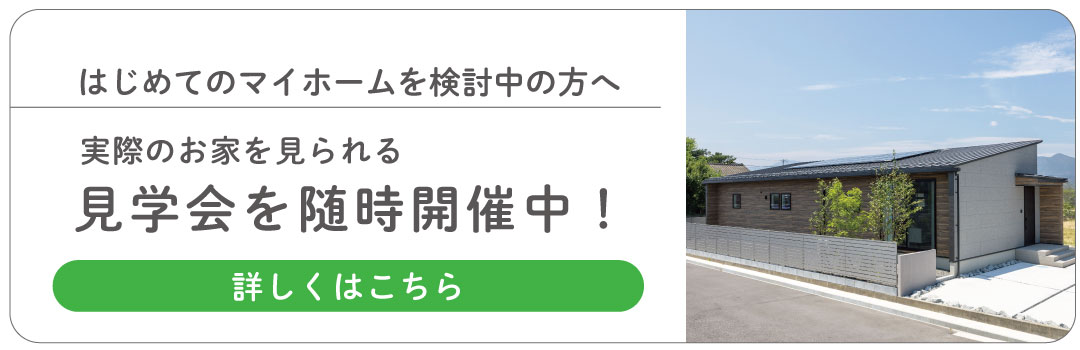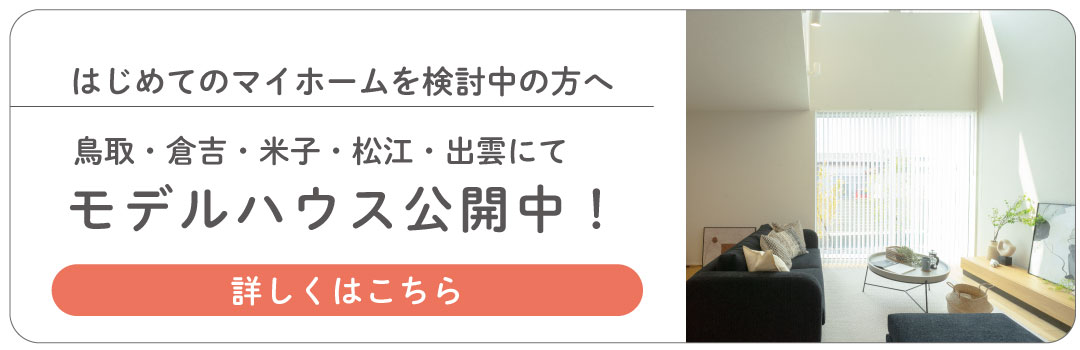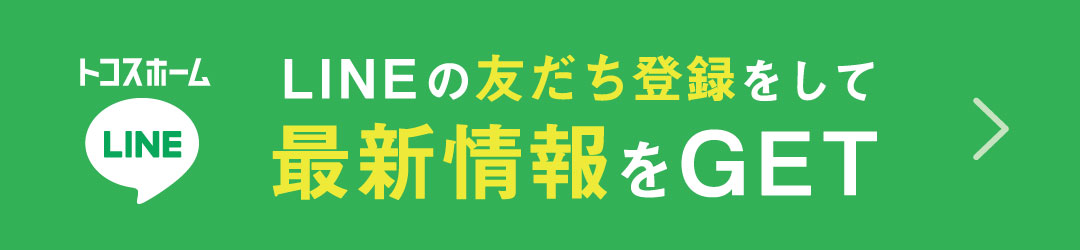住宅ローン月いくら払う?年収別の平均返済額や無理のない組み方を解説

目次
マイホームの購入を検討している方にとって、「住宅ローンは月々いくら払うのが適切なのか」という疑問は、最も重要な検討事項の一つではないでしょうか。理想の住まいを手に入れたいという思いと、毎月の生活を圧迫しない返済計画のバランスを取ることは、決して簡単ではありません。
本記事では、データを基に、実際に住宅ローンを組んでいる方々の平均的な月々の返済額を物件種別や年収別に詳しく解説します。さらに、返済額を決定する重要な要素や、無理のない住宅ローン計画を立てるための注意点についても具体的にお伝えしていきます。
住宅ローンの月々の平均返済額はいくら?

住宅ローンを組む際、多くの方が「他の人は月々いくら払っているのだろう」と気になることでしょう。実際の返済額は、購入する物件の種類や価格、年収などによってさまざまですが、国土交通省が公表している公的データから平均的な数値を把握することができます。
これから、物件の種類別の平均返済額や、年収に応じた返済額の目安を詳しく見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせることで、適切な返済計画を立てる参考にしていただけます。
【物件種別】みんなが支払っている月々のローン平均額
国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」によると、住宅の種類によって月々の返済額には大きな差があることがわかります。以下の表は、物件種別ごとの平均年間返済額と月間返済額をまとめたものです。
| 住宅の種類 | 平均年間返済額 | 平均月間返済額 |
| 注文住宅 | 144.8万円 | 12.0万円 |
| 分譲戸建住宅 | 132.1万円 | 11.0万円 |
| 分譲集合住宅 | 126.5万円 | 10.5万円 |
| 既存(中古)戸建住宅 | 109.3万円 | 9.1万円 |
| 既存(中古)集合住宅 | 114.0万円 | 9.5万円 |
| リフォーム住宅 | 73.7万円 | 6.1万円 |
この表から、注文住宅の返済額が最も高く、月々約12万円となっていることがわかります。これは、土地の購入も含めた総額が高くなることや、自由設計による建築費の上昇が要因として考えられます。
一方で、中古住宅の場合は新築に比べて購入価格が抑えられるため、月々の返済額も9万円台と比較的低くなっています。ただし、中古物件の場合は購入後のリフォーム費用や修繕費用が別途必要になることも考慮しておく必要があります。
また、住宅ローンの平均返済期間は30年前後となっており、長期にわたる支払い計画を立てることが一般的です。特に新築物件では35年ローンを組む方が多く、月々の返済負担を軽減しながら、マイホームを手に入れているケースが多く見られます。
【年収別】月々の住宅ローン返済額の目安
年収に応じた適切な返済額を知ることは、無理のない住宅ローン計画を立てる上で非常に重要です。以下の表は、年収別に返済比率(年収に占める年間返済額の割合)ごとの月々の返済額を示したものです。
| 年収 | 返済比率 | |||
| 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 300万円 | 6万2,500円 | 7万5,000円 | 8万7,500円 | 10万円 |
| 400万円 | 8万3,333円 | 10万円 | 11万6,667円 | 13万3,333円 |
| 500万円 | 10万4,167円 | 12万5,000円 | 14万5,833円 | 16万6,667円 |
| 600万円 | 12万5,000円 | 15万円 | 17万5,000円 | 20万円 |
| 700万円 | 14万5,833円 | 17万5,000円 | 20万4,167円 | 23万3,333円 |
| 800万円 | 16万6,667円 | 20万円 | 23万3,333円 | 26万6,667円 |
| 900万円 | 18万7,500円 | 22万5,000円 | 26万2,500円 | 30万円 |
| 1,000万円 | 20万8,333円 | 25万円 | 29万1,667円 | 33万3,333円 |
返済比率は、年収に占める年間返済額の割合を表すもので、金融機関の審査では一般的に30~40%が上限とされています。しかし、実際の生活を考慮すると、返済比率は25%程度に抑えることが理想的とされています。
たとえば、年収600万円の方が返済比率25%で住宅ローンを組む場合、月々の返済額は12.5万円が目安となります。これは、生活費や将来の貯蓄、急な出費にも対応できる余裕を持たせた計画といえるでしょう。
返済比率を高く設定すれば、より高額な物件を購入することも可能ですが、日々の生活や将来の不測の事態に備える余裕がなくなってしまうリスクも高まります。自身の生活スタイルや将来設計を考慮して、適切な返済比率を選択することが大切です。
住宅ローンの月々の返済額を決める重要な要素
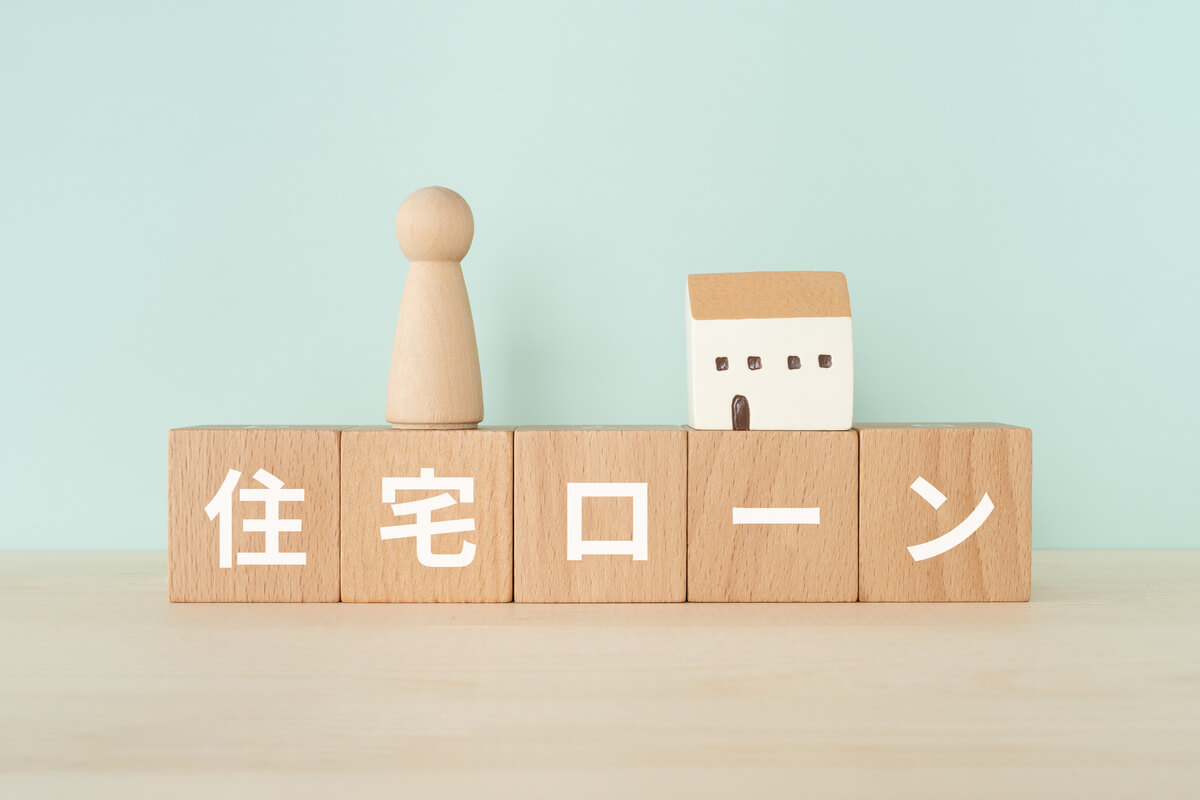
住宅ローンの月々の返済額は、単に借入額だけで決まるわけではありません。返済期間や金利タイプ、頭金の有無など、複数の要素が複雑に絡み合って決定されます。
これらの要素をそれぞれ理解し、適切に組み合わせることで、ご自身にとって最適な返済計画を立てることが可能になります。以下、それぞれの要素がどのように返済額に影響を与えるのか、具体的なシミュレーションを交えながら詳しく解説していきます。
借入額と返済期間の関係性を理解する
同じ金額を借り入れても、返済期間によって月々の返済額は大きく変わります。以下のシミュレーションで、その違いを具体的に見てみましょう。
【シミュレーション】返済期間による返済額の変化
前提条件
- 借入額:3,000万円
- 金利(固定):1.0%
- 返済方法:元利均等返済
- ボーナス払い:なし
| 返済期間 | 毎月の返済額 | 返済総額 |
| 20年 | 約13万8,000円 | 約3,311万円 |
| 30年 | 約9万6,000円 | 約3,474万円 |
| 35年 | 約8万5,000円 | 約3,557万円 |
この表から分かるように、返済期間を35年にすると月々の返済額は8.5万円となり、20年の場合と比べて約5.3万円も少なくなります。しかし、総返済額を見ると、35年返済では20年返済より約246万円も多く支払うことになります。
返済期間を長くすることで月々の返済額は軽減されますが、その分支払う利息が多くなり、結果として返済総額が大きくなるという関係性があります。
返済期間を決める際には、定年退職の時期も考慮することが重要です。たとえば、35歳で35年ローンを組むと完済時は70歳となり、定年後も返済が続くことになります。将来の収入減少に備えて、できるだけ現役時代に完済できるような計画を立てることをおすすめします。
金利タイプの違いによる影響を把握する
住宅ローンの金利タイプは、月々の返済額に大きな影響を与える要素の一つです。主な金利タイプとその特徴を以下の表にまとめました。
| 金利タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |
| 変動金利型 | ・半年ごとに金利が見直される
・返済額は5年ごとに見直される |
・当初の金利が低い傾向
・市場金利が下がれば返済額も減る |
・金利上昇で返済額が増えるリスクがある
・将来の返済額が不確定 |
| 固定期間選択型 | ・一定期間(3年、5年など)金利が固定される
・期間終了後に金利タイプを再選択する |
・固定期間中は返済額が安定し、計画を立てやすい | ・期間終了後に金利が上昇すると返済額が増える
・返済額の上昇に上限がない |
| 全期間固定型 | ・借入時から完済まで金利が変わらない | ・完済までの返済額が確定し、家計管理が非常にしやすい
・金利上昇のリスクがない |
・他のタイプより金利が高めに設定されがち
・市場金利が下がっても返済額は変わらない |
近年では変動金利を選択する人が多く、2024年4月の調査では全体の68.1%が変動金利型を利用しています。
ただし、2024年3月に日銀がマイナス金利政策を解除したことで、今後金利が上昇する可能性も考慮する必要があります。変動金利を選択する場合は、将来の金利上昇に備えて、ある程度の余裕を持った返済計画を立てることが重要です。
変動金利の場合、5年ルールや125%ルールといった制度により、急激な返済額の増加は抑えられますが、それでも長期的には返済負担が増える可能性があることを理解しておく必要があります。
頭金の有無がもたらす変化を知る
頭金(自己資金)を用意することは、住宅ローンの返済負担を軽減する効果的な方法の一つです。頭金を用意することによる具体的なメリットは以下のとおりです。
- 借入額が減少し、月々の返済額を抑えることができる
- 総返済額が少なくなり、支払う利息を削減できる
- 住宅ローン審査において有利に働く可能性がある
- 金融機関によっては、頭金10%以上で金利優遇を受けられる場合がある
国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」のデータを見ると、新築の注文住宅では購入価格の23%、中古住宅では30~35%程度の頭金を用意している世帯が多いことがわかります。
しかし、頭金を貯めることに時間をかけすぎると、以下のようなデメリットも生じる可能性があります。
まず、頭金を貯める期間中も家賃を支払い続ける必要があり、その分の支出が発生します。また、理想の物件が見つかったタイミングで購入できない可能性もあるでしょう。さらに、手持ち資金をすべて頭金に充ててしまうと、急な出費に対応できなくなるリスクもあります。
頭金の準備については、無理のない範囲で計画的に行い、生活防衛資金として最低でも3~6ヶ月分の生活費は手元に残しておくことが大切です。
無理のない住宅ローン計画を立てるための注意点

住宅ローンを組む際には、目先の返済額だけでなく、長期的な視点で計画を立てることが重要です。多くの方が見落としがちなポイントや、将来後悔しないための注意点について解説していきます。
「借りられる額」と「無理なく返せる額」は異なります。金融機関の審査に通る金額と、実際に生活を維持しながら返済できる金額には差があることを理解し、ライフプラン全体を見据えた健全な資金計画を立てることが大切です。
関連記事:家づくりは何から始める?注文住宅を建てる流れや期間をわかりやすく解説
理想的な返済比率で計画する
金融機関の審査では、一般的に返済比率を25~30%程度を目安としていますが、実際には20~25%程度に抑えることが理想的とされています。この違いには重要な理由があります。
金融機関が用いる返済比率は、額面年収(税金や社会保険料が引かれる前の年収)を基準に計算されます。しかし、実際に使えるお金は手取り年収であり、額面年収の約75~80%程度になることが一般的です。
たとえば、額面年収600万円の方の手取り年収は約450万円程度となります。額面年収で返済比率30%(月15万円)の計画を立てると、手取り年収では実質40%近い負担となってしまうのです。
手取り年収で計算することが重要な理由は、実際の生活費や貯蓄に回せる金額を正確に把握できるからです。税金や社会保険料は年々増加傾向にあり、将来的に手取り額が減少する可能性も考慮しておく必要があります。
また、返済比率には住宅ローン以外の借り入れ(自動車ローン、教育ローンなど)も含まれることにも注意が必要です。すでに他のローンがある場合は、その返済額も含めて総合的に判断することが求められます。
ライフプランを考慮した資金計画を立てる
住宅ローンの返済期間は30年以上に及ぶことが多く、その間にはさまざまなライフイベントが発生します。これらを事前に想定し、資金計画に組み込んでおくことが重要です。
主な考慮すべきライフイベントとして、子どもの教育資金があげられます。大学進学時には入学金や授業料で数百万円が必要になることもあり、この時期と住宅ローンの返済が重なると家計への負担が大きくなります。
車の買い替えも定期的に発生する大きな支出です。一般的に10年前後で買い替えを検討することが多く、その都度まとまった資金が必要になります。
老後資金の準備も忘れてはいけません。住宅ローンの返済に追われて老後の備えができていないと、定年後の生活が困難になる可能性があります。
完済時年齢も重要な検討事項です。35歳で35年ローンを組むと完済は70歳となり、定年退職後も返済が続くことになります。退職後は収入が大幅に減少することが予想されるため、できるだけ現役時代に完済できるような計画を立てることが理想的です。
将来的な収入の変動も考慮すべきポイントです。昇給や昇進による収入増加が期待できる一方で、転職や病気による休職など、収入が減少するリスクも存在します。こうした不確実性に備えて、返済額には余裕を持たせておくことが大切です。
関連記事:【2025年最新】長期優良住宅の補助金・住宅ローン減税・税制優遇を解説
住宅維持費の見落としに注意する
住宅を所有すると、ローン返済以外にもさまざまな維持費が発生します。これらの費用を見落として返済計画を立ててしまうと、将来的に家計が圧迫される可能性があります。
固定資産税は、土地と建物の評価額に応じて毎年課税される税金です。新築住宅の場合、年間10~20万円程度かかることが一般的で、都市計画税が課税される地域では、さらに負担が増えます。
火災保険料や地震保険料も必要な支出です。近年は自然災害の増加により保険料が上昇傾向にあり、年間数万円から十数万円の負担となることもあります。
将来の修繕費用も計画的に準備する必要があります。築10年を過ぎると、外壁塗装や屋根の補修、給湯器の交換など、まとまった費用が必要になってきます。これらの修繕を怠ると住宅の寿命が短くなるため、定期的なメンテナンスは欠かせません。
マンションの場合は、これらに加えて管理費と修繕積立金が毎月発生します。新築時は比較的安価でも、築年数が経過するにつれて値上がりすることが多いため、将来的な負担増も想定しておく必要があります。
これらの住宅維持費を合計すると、年間で数十万円の支出となることも珍しくありません。住宅ローンの返済額を決める際は、これらの維持費も含めた総合的な住居費として考えることが、無理のない資金計画につながります。
【鳥取・島根】注文住宅の資金計画はトコスホームへ
住宅ローンの月々の返済額について、平均的な数値や適切な計画の立て方を詳しく解説してきました。物件種別や年収に応じた返済額の目安、返済期間や金利タイプによる影響、そして見落としがちな住宅維持費まで、総合的に考慮することで、無理のない住宅ローン計画を立てることができます。
トコスホームでは、初期費用だけでなく入居後の光熱費やメンテナンス費まで含めた「トータルコスト」を考慮した家づくりをご提案しています。単に購入時の価格だけでなく、長期的な視点で経済的な住まいを実現することが、本当の意味での「良い家」だと考えているからです。
国の基準を大きく上回る高気密・高断熱性能により、年間の光熱費を大幅に削減できることも大きな経済的メリットです。一般的な住宅と比較して、年間10万円以上の光熱費削減も可能で、35年間では350万円以上の差額となります。この削減分を住宅ローンの返済に充てることで、実質的な負担を軽減することができるのです。
さらに、最長60年の長期保証など、建てた後も安心して暮らせるサポート体制を整えています。定期的な点検と適切なメンテナンスにより、住宅の資産価値を長期間維持し、将来の大規模修繕費用を抑えることも可能です。
鳥取・島根で注文住宅をご検討の方は、ぜひトコスホームにご相談ください。お客様のライフプランに合わせた無理のない資金計画から、快適で経済的な住まいづくりまで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。