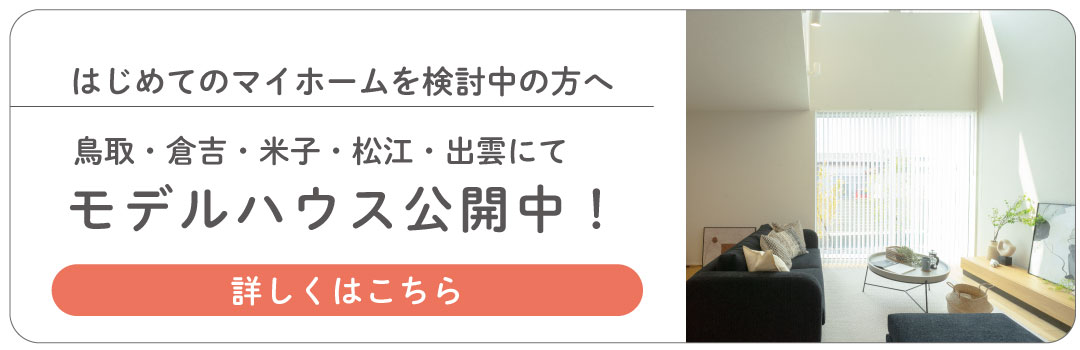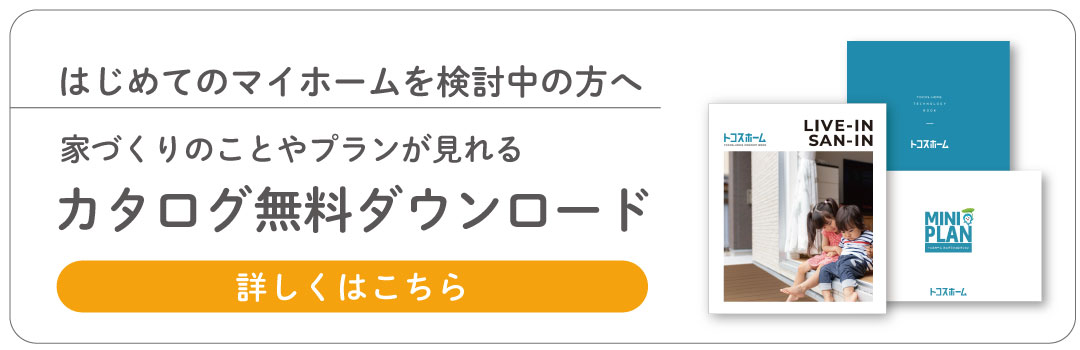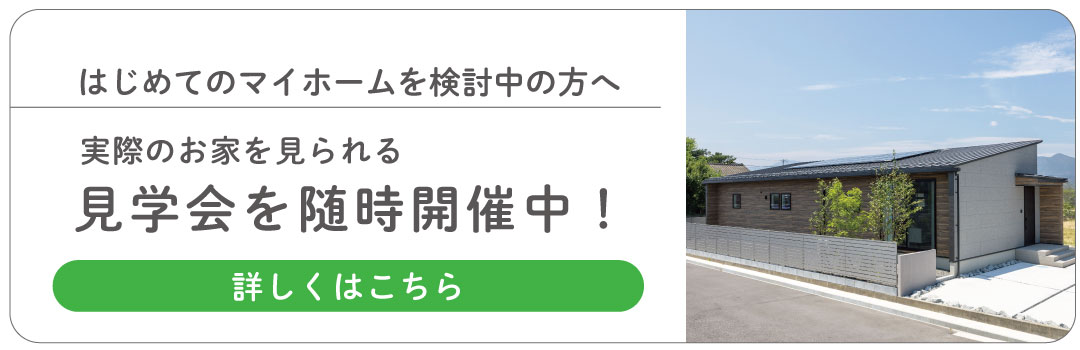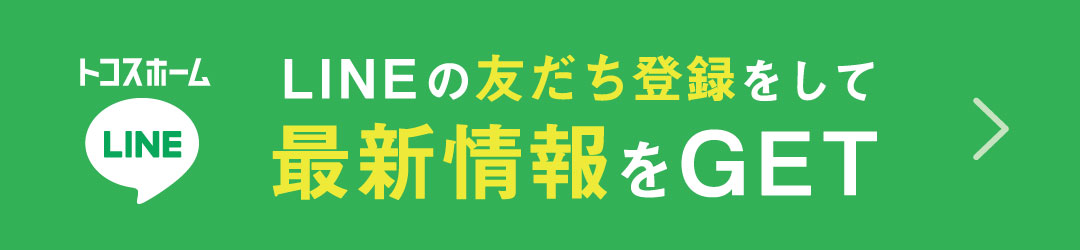ZEH基準の断熱等級5は寒い?等級6・7との違いや基準を解説

目次
「ZEH基準の断熱等級5の家は本当に快適なの?」「寒いという評判を聞くけど実際はどうなの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。省エネ住宅として注目されるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の断熱基準である「断熱等級5」について、その実際の性能や住み心地を正しく理解することは、これから家づくりを始める方にとって非常に重要です。
本記事では、断熱等級5の具体的な性能基準から、より高性能な等級6・7との違い、そして将来を見据えた住宅選びのポイントまでを詳しく解説します。
断熱等級5の基本とZEH・長期優良住宅との関係

断熱等級5について正しく理解するためには、まず断熱等級そのものの仕組みと、ZEHや長期優良住宅といった他の住宅制度との関連性を知ることが重要です。国の省エネ化推進に伴い、これらの基準は密接に関係しており、それぞれが日本の住宅性能向上において重要な役割を果たしています。
そもそも断熱等級とは?UA値と地域区分で決まる性能指標
住宅の断熱性能を示す「断熱等級(断熱等性能等級)」は、1〜7の7段階で評価される基準です。数字が大きいほど高性能であり、より優れた断熱性能を持つ住宅となります。
等級を判定するための主要な指標は「UA値(外皮平均熱貫流率)」と「ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)」の2つです。UA値は室内と外気の熱の出入りのしやすさを表す数値で、ηAC値は太陽からの日射熱が室内にどれだけ入りやすいかを示す数値となっています。いずれも数値が小さいほど熱が出入りしにくく、断熱性能が高いことを意味します。
日本全国は気候に応じて8つの地域に区分されており、地域ごとに求められる断熱性能の基準が異なります。これは、北海道のような寒冷地と沖縄のような温暖地では、必要な断熱性能が大きく異なるためです。
| 地域区分 | 主な該当地域 | 代表的な都市の例 |
| 1地域 | 北海道の大部分(寒冷地) | 旭川市など |
| 2地域 | 北海道の一部(寒冷地) | 札幌市など |
| 3地域 | 東北・北関東の一部 | 盛岡市など |
| 4地域 | 関東・東海の一部 | 松本市など |
| 5地域 | 関東・東海・近畿の多く | 宇都宮市など |
| 6地域 | 近畿・中国・四国の一部 | 東京都など |
| 7地域 | 九州・四国の一部 | 鹿児島市など |
| 8地域 | 沖縄(温暖地) | 沖縄 |
ZEH水準に相当する断熱等級5の性能基準
2022年4月に新設された断熱等級5は、省エネ住宅であるZEHの断熱基準に相当します。ZEHは、年間のエネルギー消費量を太陽光発電などの創エネルギーで相殺し、実質ゼロ以下にすることを目指す住宅です。
断熱等級5の具体的な性能として、冬場に「室温が概ね10℃を下回らない程度」の断熱性が確保されることが基準となっています。10℃という温度は、室内でもアウターを着たいと感じる温度感であるため、高効率な暖房器具などと組み合わせることで快適な室温を保つ工夫が必要となります。
ZEHは断熱性能だけでなく、高効率な省エネ設備(LED照明、高効率エアコン、エコキュートなど)と太陽光発電などの創エネ設備を組み合わせることで、年間のエネルギー収支を実質ゼロ以下にすることを目標としています。そのため、断熱等級5はZEHを実現するための最低限必要な断熱性能という位置づけになっています。
長期優良住宅に求められる断熱性能との関連性
長期間にわたり良好な状態で住み続けられる「長期優良住宅」の認定基準においても、2022年10月から断熱等級5以上が必須条件となりました。これは、住宅の長寿命化には高い断熱性能が不可欠であるという認識が広まった結果です。
長期優良住宅は断熱性だけでなく、高い耐震性(耐震等級2以上)、劣化対策等級3相当、維持管理対策等級3(専用配管)、住戸面積75㎡以上など、複数の厳しい基準をクリアした高品質な住宅です。これらの性能を総合的に満たすことで、世代を超えて安心して住み続けられる住まいとなります。
長期優良住宅の認定を受けることで、住宅ローン減税の控除額拡大(最大4,500万円)、固定資産税の減税期間延長(戸建てで5年間)、登録免許税の軽減など、多くの金銭的メリットを享受できます。
長期優良住宅については以下の記事でも解説していますので、ぜひご参照ください。
関連記事:【2025年最新】長期優良住宅の補助金・住宅ローン減税・税制優遇を解説
断熱等級5は寒い?上位等級との性能差を徹底比較

断熱等級5はZEH基準であり、決して低い性能ではありません。しかし、住む地域や個人の体感によっては「寒い」と感じる可能性があるのも事実です。その理由は、2022年10月に新設された、さらに高性能な「断熱等級6」「断熱等級7」との性能差にあります。ここでは、それぞれの等級の違いを詳しく見ていきましょう。
断熱等級5の住宅で寒さを感じるケース
断熱等級5の基準である「室温10℃」は、室内でもアウターを着たくなる温度感です。特に暖房をしていない廊下やトイレなどで寒さを感じる可能性があります。リビングは暖房で快適でも、一歩廊下に出ると急に寒くなるという温度差が生じやすいのです。
寒冷地では、温暖な地域と同じ断熱等級5でも基準となるUA値が厳しく設定されています。しかし、外気温が低いため、暖房のない空間との温度差が広がりやすい傾向があります。たとえば、北海道の住宅では、同じ断熱等級5でもUA値0.4という高い基準が求められますが、外気温がマイナス10℃以下になることもあるため、暖房していない空間では体感的な寒さを感じることがあるのです。
また、部屋ごとの大きな温度差は、体に負担をかける「ヒートショック」のリスクを高めます。日本では、入浴中の死亡者数は年間19,000人いるとも推計されており、これは交通事故死者数を大きく上回る深刻な問題です。この数には転倒による死亡者数も含まれているため、すべてがヒートショックによるものではありませんが、家全体の断熱性能を高めることは、快適性だけでなく健康面でも極めて重要といえるでしょう。
断熱等級6・7との室内温度環境や体感の違い
断熱等級5、6、7が目標とする冬場の最低室温には、以下にように明確な違いがあります。
| 断熱等級 | 最低室温の目安 |
| 断熱等級5 | 概ね10℃を下回らない |
| 断熱等級6 | 概ね13℃を下回らない |
| 断熱等級7 | 概ね15℃を下回らない |
断熱等級5よりも室内温度環境が高い断熱等級6や7では、アウターを羽織らなくても快適に過ごせそうな室温です。特に断熱等級7では、体感温度が15℃未満となる割合が2%未満とされており、断熱等級5とは大きな差があります。
世界保健機関(WHO)は、健康のために冬の室温を18℃以上に保つことを推奨しています。この基準から見ると、断熱等級7の「概ね15℃を下回らない」という性能は、暖房の使用を前提としても、健康的な室内環境を実現しやすい水準といえます。一方、断熱等級5の「10℃」では、暖房への依存度が高くなり、光熱費の負担も大きくなることが予想されます。
省エネ性能で見る断熱等級ごとの違い
断熱等級と省エネ住宅基準の関係性は以下の通りです。
- ZEH:断熱等級5相当
- HEAT20 G2:断熱等級6相当
- HEAT20 G3:断熱等級7相当
等級4の住宅と比較して、断熱等級5は約20%、等級6は約30%、等級7は約40%のエネルギー消費量を削減できるとされています。この差は年間の光熱費に換算すると、数万円から十数万円の違いとなって現れます。
高い断熱等級の住宅は、初期の建築費用は高くなる傾向があります。しかし、その後の光熱費を大幅に削減できるため、長期的な視点で見ると経済的メリットが大きくなります。10〜20年程度で初期投資の差額を回収でき、その後は継続的に省エネによる恩恵を受けることができるのです。HEAT20については、以下の記事で詳細に解説しています。
関連記事:HEAT20とは?従来の断熱基準との違いや地域区分をわかりやすく解説
これからの家づくりで目指すべき断熱性能

断熱等級5、6、7の性能差を比較すると、将来を見据えた家づくりでは、より高い性能を目指すことが重要であることがわかります。ここでは、今後の法改正の動向を踏まえ、どのような断熱性能を目指すべきかを解説します。
2025年・2030年の義務化を見据えた住宅選びの重要性
2025年4月からすべての新築住宅で「断熱等級4」以上が義務化されます。さらに2030年度には「断熱等級5」が最低基準になることが決まっています。つまり、現在はZEH基準として高い性能に位置づけられている断熱等級5が、わずか数年後には法的な最低ラインとなるのです。
住宅の寿命は一般的に30〜60年といわれています。数十年という長いスパンで考えると、現在の最低基準である断熱等級4や、数年後に最低基準となる断熱等級5で建てた住宅は、将来的に「性能の低い住宅」として評価される可能性があります。これは資産価値の面でも大きな影響を与えるため、注意が必要です。
将来のスタンダードとなり得る「断熱等級6」以上を視野に入れて家づくりを進めることが、長く快適に暮らすための賢い選択といえるでしょう。断熱等級6の住まいは、断熱等級5と比べて快適性や省エネ性が高まり、断熱等級7よりも建築費用を抑えられるバランスの取れた選択肢といえます。
住宅の断熱性能を高めるための具体的な工法
断熱性能を高めるためには、以下の4つのポイントを押さえることが重要です。
- 質の高い断熱材を、適切な厚みと施工方法で隙間なく施工すること
どんなに良い断熱材でも薄くて隙間だらけの施工では、高い断熱性は確保できません。性能の高い断熱材を標準仕様とし、高い技術力で施工してくれる住宅会社を選ぶことが大切です。
- 熱の出入りが最も多い窓や玄関ドアは、トリプルガラスや樹脂サッシといった高性能な製品を選ぶこと
断熱性の低い家では、冬場は58%の熱が開口部から逃げ、夏場は73%の熱が開口部から入るというデータがあります。高性能な窓や玄関ドアの採用は、断熱性能向上の要となります。
- 軒(のき)や庇(ひさし)を設けて、夏は強い日差しを遮り、冬は暖かい日差しを取り込めるように日射量をコントロールすること
軒や庇は、夏場の強い日差しを遮り、冬場の日差しを取り込むことができます。パッシブデザインの考え方を取り入れることで、機械に頼らない快適性を実現できます。
- 換気による熱損失を最小限に抑えられる熱交換型の「第一種換気システム」を採用すること
給気と排気の際に熱交換をしてくれる第一種換気システムなら、排気に含まれる熱を回収し、給気した空気に伝えることで、冷たい外気温の侵入を防げます。熱の出入りを最小限に抑えることが可能です。
これらの対策を組み合わせることで、設計上のUA値だけでなく、実際の住み心地を大きく向上させることができます。高性能住宅については、以下の記事でも解説しています。
関連記事:家の性能とは?松江市の子育て世帯必見!家づくりのポイント
標準仕様で高い断熱等級をクリアする住宅会社の選び方
これからのスタンダードになり得る断熱等級6以上を目指す場合、その性能を「標準仕様」としている住宅会社を選ぶことがコスト面でも品質面でも重要です。施工会社によっては断熱等級6以上に対応できない、あるいはオプションとして高額な追加費用がかかるケースもあるため、施工実績が豊富で技術力の高い会社を見極める必要があります。
トコスホームでは、標準仕様でHEAT20 G2レベルを超えるUA値0.4を実現しています。これは断熱等級6を上回る高い性能であり、鳥取・島根の厳しい気候条件を知り尽くした「山陰スタンダード」として、地域に最適化された高性能住宅を適正価格で提供しています。最長60年保証という充実したアフターサポートと合わせて、世代を超えて快適に暮らせる住まいづくりをサポートしています。
【鳥取・島根】で注文住宅を建てるならトコスホームへ
ZEH基準の断熱等級5は、現在の基準では高性能な部類に入りますが、実際の住み心地では「寒い」と感じる可能性があることがわかりました。2030年には最低基準となることを考えると、これから家づくりをされる方は、断熱等級6以上を目指すことが、長期的な快適性と経済性の両面から賢明な選択といえるでしょう。
高い断熱性能は、単に寒さを防ぐだけでなく、家族の健康を守り、光熱費を削減し、住宅の資産価値を維持する重要な要素です。将来を見据えた家づくりを実現するためにも、高い技術力と豊富な実績を持つ住宅会社選びが成功の鍵となります。
鳥取・島根エリアで高断熱・高気密の注文住宅をご検討の方は、ぜひトコスホームにご相談ください。山陰の気候に最適化された高性能住宅で、世代を超えて快適に暮らせる住まいづくりをお手伝いいたします。